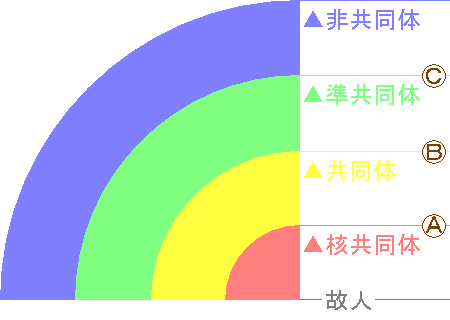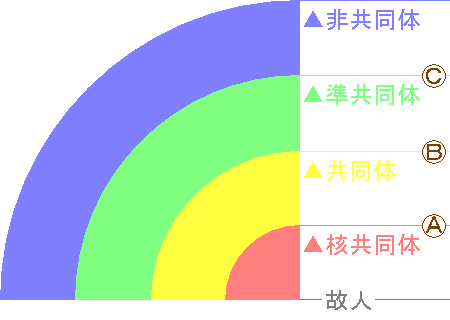私家辞書(用語再定義)
▽ 閲覧上の注意
このカテゴリーは、筆者が葬儀に関する用語をどう理解すべきか考え、自身の内における再定義を述べたものです。
そのため、用語の解釈は一般的でない可能性が多分にあります。
閲覧の際はその点にご留意いただくとともに、誤りを発見された場合やご意見がございましたらお知らせいただければ幸いです。
《 葬儀 》
▽ 用語再定義
《葬儀》とは、「ある共同体において継続的に共有されてきた死者の葬りと弔いに関するしきたりの総体のこと。また、現代では特にその中心的な役割を果たす葬式のこと。」である。
▽ 再定義に至る思索
ある共同体において継続的に共有されてきた〜しきたり
「葬儀とは死者の葬りの儀式・儀礼である」と説明されることが多いが、儀式・儀礼とは何であろうか。特段に宗教などにおける儀式・儀礼は理解しやすいとしても、葬りに関わる儀式・儀礼がすべて宗教性を帯びているかと言えばそうではない。
儀式・儀礼の本義は、一定の決まり事に従って行われる行事・作法のことであろう。一定の決まり事である以上、決まり事を定めるある社会、ある共同体の中における慣習に依る。宗教における儀式も、それは宗教という共同体における決まり事、慣習である。
共同体における決まり事・慣習は、経年による変化は当然としても少なくともその共同体の連続性の中で成立してゆくものである。例えば、ある共同体が既存の慣習を突然すべて放棄して新しい決まり事を作ったとすれば、それはなお旧来と同じ共同体であるとは言い難いのではないか。
また、共同体の中においても共有されない物事は決まり事の体を成さず、それはあくまでも個別の行為である。
それらのことから言って、「儀」は「ある共同体における」こと、「継続的である」こと、「共有される」ことを満たすべきであり、それを説明するには特定の宗教・思想によるものを想像しやすい「儀式・儀礼」よりも、広範に解せられることの多い「しきたり」という用語の方が適当ではないかと考えられる。
死者の葬りと弔い
「葬り」と「弔い」は異なるものである。しかしたとえある一時期やある共同体において、そのどちらかが存在しない(*1)としてもそれは局部的であり、大局的に見て「葬り」と「弔い」は相互に密接に関連し切り離し難いものであると考えてよいだろう。
そのことから、「儀」の主体として「葬り」と「弔い」は並記されるべきであると考えられる。また、この「葬り」と「弔い」のセットを「葬送」と呼んでもよいだろう。
(*1) 平安時代の京における死体放置の常態化や、現代における単純死体処理など
総体
「儀」は当然、各々の共同体において様相を異にするものである。ならば、単純に「葬儀」と言う場合には総論を述べるべきであって、各論を述べる場合には「いついつのどこどこにおける葬儀」と言うことが肝要である。
さらに、葬儀は瞬間的な物事ではない。たとえばもし、死体処理という瞬間的な物事だけを論じるならば、それは葬儀と呼ぶべきではない。また、納棺・葬式・火葬・埋骨などの要素についてそれぞれを単独で取り出してもそれは個別の物事であって、その全体をして初めて「葬儀」と呼ぶべきであろう。
現代では特にその中心的な役割を果たす葬式
「葬儀」は日本語である。従って、その語の解釈には日本における葬送文化が絡むのは当然のことである。
近年の日本においては旧来の慣習、特に葬列の装飾(*2)、土葬や野焼きの作法(*3)など、また遺された者のグリーフワークのための機能(*4)などが、「葬式」の中に集約されているという現状がある。
そのため、旧来は相当期間をかけて行われた「葬儀」も、短時間化した「葬式」がそのほとんどであるように理解されることが一般的になり、「葬儀=葬式」という構図を生んだことは自然な経緯であると言える。
そのことの是非はともかくとして、語に対しそのような理解があることは認めなければならないだろう。
(*2) 仏教葬儀における祭壇の棺前(白木宮)や六灯など
(*3) 仏教葬儀において引導作法で松明を用いることなど
(*4) 時間としての通夜や、焼香や献花など
▽ 発展的思索
一般的に、「死」と「葬儀」はセットで考えられることが多い。しかし、「死」と「葬儀」は密接に関連してはいても、その根本において性質のまったく異なるものである。
「死」が人間にとって超越的な事象──キリスト教では神のわざ、仏教ではダルマ(法)の定め、神道では自然の摂理、など──であるのに対し、葬儀は「人のわざ」であるからだ。
なぜならば、「死」は万人に必ず訪れるものであるが、死んだ者が必ず葬られ弔われるわけではないからである。
さらに言えば、「葬儀」が「宗教的行為」であるのは「その信仰共同体において」であって、「総体としての葬儀」は「社会的行為」であると言える。
たとえ葬儀において宗教が特段に重要だとしても、宗教的行為のみが葬儀であるならば、宗教に依らない共同体の中における葬りや弔いは葬儀ではないと言わざるを得なくなるからであり、そしてそれは現代社会において必ずそうだとは言い難いからである。
そこで、現存する思想・宗教・哲学として(*5)の「死学(*6)」だけでなく、社会学としての「葬儀学」も形成されて良いのではないか。すなわち、「人はどう生き、死ぬか」や「人は死んだらどうなるか」ではなく、死を普遍的前提として「人はどう葬り弔うのか、あるいは葬り弔わないのか」を総体的・客観的に学問するのである。
ある国の国民がほとんど同じ宗教を持っているなら、ここで言う「死学」と「葬儀学」はほぼ同じものになるだろうから、これはむしろ日本において形成の可能性がある学問ではなかろうか。
(*5) 関連的に社会的側面から見た葬儀についても言及することはある
(*6) 日本では「死生学」と呼ばれることが多いが、現代日本における葬儀論者の第一人者である碑文谷創師は「一般語としては、あくまで『死学』である方がよい」と主張しており、私もそう思う
▽ 現代日本キリスト教における『葬儀』
キリスト教における「葬儀」とはなんであろうか。現在日本でこの質問をすると、九分九厘「葬儀は礼拝である」と返ってくるだろう。しかし、本当にこれで十分だろうか。
当然、「葬儀は礼拝である」とは神学的側面から言われることであるから、ここで言われる「葬儀」にこの再定義を当てはめるならば、「キリスト教会という信仰共同体において〜」となる。そのため、新しい「式文(*7)」において、「教会の公同の礼拝と同じく、聖餐や信仰告白を加えるべきだ」と主張されたことについては、その前提においては私は異論をはさむ立場にない。
しかし現実において、日本におけるキリスト教はマイノリティ宗教である。共同体の範囲が限定されている修道院などではともかく、日本におけるキリスト教葬儀はその多くの場合において、「信仰共同体を中心とした」営みではあっても「信仰共同体のみ」の営みではあり得ない。葬儀が共有された時空間であるならば、信徒のみが参加する(*8)聖餐や信仰告白を導入することが、その点において故人を中心とした他の共同体(*9)に属する人々を排除するよう機能してしまう可能性があることは自明であろう。
(*7) 日本キリスト教団出版局発行 日本基督教団信仰職制委員会編 「日本基督教団 式文(試用版)」2006年10月
(*8) 信徒以外でも聖餐に与れるかどうかは現在も議論のあるところであるが
(*9) 例えば、直近の共同体である家庭においても信仰を共有しているとは限らない
そのため、現実を踏まえて的確に表現しようとするならば、「『我々キリスト者』は、葬儀においても礼拝を中心とすべきである。」と言うべきではなかろうか。すなわち、現代日本において「キリスト教の葬儀とは何か」と考える場合には、必ずその前提として「現在の日本」という社会共同体の存在を認識すべきである。あるいはそれが譲れないならば、信徒による「礼拝」と社会による「葬儀」を時空間を異にするものとして切り分ける必要があるだろう。
もっともこの二者は、必ずどちらかでなければならないということはなく、葬儀を構成するそれぞれの事柄について、より良い選択をすべきである。具体的には、日本的慣習に則った告別式・弔辞・弔電・献花・記念会などの適当な許容(共有)や、聖餐を葬式内ではなく「キリスト者の末期病床において本人と共に」、また葬儀後に「教会(信仰共同体)内で記念して」行う(切り分け)などである。
葬儀においては、「葬儀を行う共同体」として「故人を中心とした、信仰共同体と社会共同体を含めた共同体」を認識として設定するべきである。すなわち、信仰共同体は社会共同体を「お客さん」にしてはならない。ましてや、「故人の信仰」を言い訳に自分たちのアイデンティティを守るだけであっては、葬儀の意義を十分に果たせるだろうか。
我々は「日本で生きて死ぬキリスト者」であると再認識しつつ、これからの日本におけるキリスト教葬儀を考えていかなければならないだろう。
それでもこれは抑圧ではない。極端なことを言えば、我々キリスト者が御国に入れられるかどうかは、葬儀の「キリスト教性」に依るのではない。「主にあって死ぬ(*10)」かどうかではないのか。
(*10) 黙示録 14:13
▽ 反省
たとえこうして社会的葬儀を前提に考える以上、私が死者(*11)のかしら(頭領)だとしても、私は「葬儀士」として信仰共同体に属さない遺族にも寄り添うことが職業的使命である。やはり天のもの(主の民の共同体)と地のもの(社会共同体)に共に仕える道はないのだろうか。キリスト者は社会的に葬儀士たり得ないのであろうか。これは、私の職業人生をかけて取り組むべき設問であろう。
牧会に力を注がれる諸先生方へ失礼にも意見することを反省しつつ。
(*11) ルカ 9:60
《 家族葬 》
▽ 用語再定義
《家族葬》とは、「故人の晩年の生活における最小単位の共同体構成員のみを葬儀主体として営まれる葬儀のこと。」である。
▽ 再定義に至る思索
現在「家族葬」という語は葬儀業界においても消費者間においても画一的な見解を持たれていない語であり、葬儀(特に葬式)においてしばしばトラブルの元になっている。語の構成そのものはシンプルで「家族」+「葬儀」でしかないのであるから、このどちらかあるいは両方にトラブルの原因があるわけである。
故人の晩年の生活における最小単位の共同体構成員
そもそも「家族」とは何か。一般的な認識においては、「同じ居宅内で生活を共にする者」であろう。ほとんどの場合、これは親子(祖父母と孫)、兄弟姉妹、夫婦などによって構成されるが、同居人やペットなどを「家族」と考えることも現代においては少なくはない。
旧来は「家(イエ、とカナ書きされることが多い)」と言えば「一族共同体」であったし、親族は比較的集中して生活していたわけであるから、「親族」と「家族」にはそう差違はなかったのだろう。しかし「家」が制度的に崩れ、親族の居住地も拡散していく中で、「遠くの親戚より近くの他人」を大切にする感覚が生まれることは無理からぬことである。
葬儀に携わる共同体の範囲そのものを考えるならば、以下の図のように分けてみるのもよいだろう。
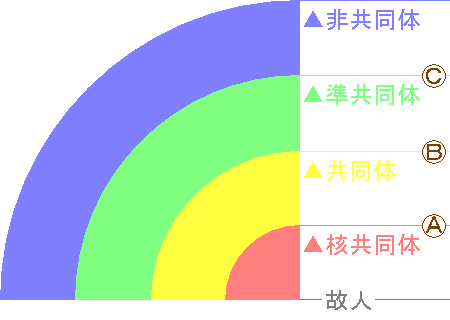 |
非共同体(C〜) | 共同体として認識し難いその他の人々 |
| 準共同体(B〜C) | 会社の人や知人など社会共同体 |
| 共同体(A〜B) | 地域共同体や信仰共同体など生活上の共同体 |
| 核共同体(故人〜A) | 生存に関わる直近の共同体 |
社会が近代化する以前においては、図でいう共同体と準共同体はほとんど同じものであったはずである。例えばある村の中で、仕事だけ関わって生活にはまったく関わらないなどということは考えにくかったであろう。つまり準共同体に位置する人はほとんどなく、村の中の人は共同体、村の外の人は非共同体とはっきりしていたはずである。
しかし近代化した社会では、準共同体の拡大にともない地域共同体などが減退していく。場合によっては、核共同体のすぐ外は準共同体であることも珍しいこととは言えなくなっているのである。
その事情から、本来はっきりと認識できていたAラインが、Bラインとあまりにも近くなったことによって認識しづらくなり、人によってはBラインまでを「直近」と考えることも現在では少なくないのであろう。
そのことから言っても、「家族」の範囲は現在においては規則的なものではなく「個々の認識による」という理解をすべきである。すなわち、トラブルの根には消費者の言う「家族」と葬儀業者の言う「家族」の範囲が時折一致しないという問題があるのであるから、葬儀業者は個々の葬儀施行に際してそれぞれに「故人の生活における最小単位の共同体」の範囲を確認する必要があるのである。
また、消費者が自分たちの言う「家族」のみで葬儀を行いたいと希望しても、それ以外の人々の会葬を断り切れないケースも多々ある。それも、消費者の言う「家族」が必ずしも故人を取り巻く人々の考える「家族」と一致しないのだということを、葬儀業者は的確にアドバイスしていく必要があろう。
そういった意味で、葬儀業者は商品としての家族葬のパッケージングに際しては丁寧な感性が必要であろうし、消費者も「家族葬=安い」という認識は持つべきでない。家族の範囲が狭ければ安くもできるし、家族の範囲が広ければ必然的に価格は上がるのである。
葬儀主体として
現在において葬儀業者を関与させない葬儀実務は現実的に困難である。従って、家族葬だからといって家族だけですべてができるわけではない。「主体として」という断りは、ただそれだけのためのものである。
そう言われてみれば、本当に家族だけですべて済ませてしまう葬儀はなんと呼ぶべきだろうか。例えば「自葬」と言えば、それは江戸〜明治時代に葬儀が仏教にのみ許された時代の、規則に反した仏教以外の葬儀のことであるし、「自由葬」と言えばそれは現在においては概ね無宗教葬の意味である。現実的には必要ないとはいえ、あり得なくはないこの事象に適当な名称はあるだろうか。
▽ 発展に向けた思索
定義の文言が長すぎる。これが最大の問題である。
理由は、これまで述べたように「家族」の定義が曖昧だからである。これさえはっきりしていれば、現在メディア上で一般に言われているように「家族葬は家族のみによって行う葬儀」で十分である。
さて、時代はこれからどう変化していくのだろうか。
《 直葬 》
▽ 用語再定義
《直葬》とは、「社会的必要によって死者の葬りのみを行うこと。」である。
▽ 再定義に至る思索
社会的必要によって死者の葬りのみを行う
先の《葬儀》で述べたように、葬儀を構成する要素には葬り・弔い・共有・連続などが挙げられるが、直葬はその内の行為としての「葬り」のみを端的に行うことである。
現在多くの場合において直葬(読みは「ちょくそう」である)は「葬式」をしない葬儀であると解釈されているが、これは妥当ではないと考えられる。なぜならば再定義「葬儀」でも考察したように、現在の葬式は葬儀を集約したひとつのスタイルであって、そのスタイルから逸脱したとしても「葬送(葬りと弔い)」の本質にもとるかどうかは別の問題だからである。
例えば、葬式は持たないが死者の枕元に線香を立て、弔いの意図を持って棺に納め、火葬するとすれば、これを私は「直葬」と呼ぶべきではないと思う。それは簡略化されているとしても「葬送」の選択しうるひとつのスタイルと言えるからである。
だから、先日「葬式は、要らない」(島田裕巳 幻冬舎新書)という本が出版されたときも、業界内では随分物議を醸したが、(私たちに理解を示してくださった皆様には申し訳なかったが)私の反応は鈍かった。「葬式」そのものについては「要か、不要か」ではそもそもない。その葬送を行う者が「するか、しないか」でしかない、と考えていたからである。(*1)
*1 もちろん、タイトルを言葉通り解釈した場合、という話で、内容のことではない。後日この本を取り上げて氏が出演したテレビを見たが、氏の言にはまったく共感できなかった。
米国に「direct cremation」という語がある。直訳すれば「直接火葬」である。海外における direct cremation の選択は、葬式の是非、特に現在の日本でしきりに議論の対象になる葬儀代金の高さに対する反発から生まれたものではなく、「葬儀に意義を感じない」という人々が具体的処理だけをすることを選択したものであると私は理解している。
すなわち直葬の「直」は何を飛び越えているかと言えば、それは「葬式」ではなく「死亡」から「死体処理」までのすべての「行為」と「意志」であろう。
▽ 発展に向けた思索
もしこの定義が理解されるならば、現在の日本における「直葬」は、相当数において適当な表現ではない。葬儀社も消費者も、「葬式をしない=安い」という意味と期待で、また時には商業戦略的にこの名称を用いることが多いからである。
私はここに現代日本葬儀のひとつの問題点があると考えている。すなわち、「葬式をしない葬儀」を売り込みながらも、「直葬」と「葬儀」は別のもの、「葬式が無ければ葬儀にあらず」という意識が少なからず社会に存在し、葬りの自由性や発展性、構造変化を暗に拒否していると考えられるからである。
「葬儀」の構成に最低限必要不可欠なものは何か。それは「ルール」ではなく、「葬りと弔いの意志」ではなかろうか。「直葬」という語の混乱には、そのような根本的な問題がかいま見える。
《 グリーフ(grief) 》
▽ 用語再定義
《グリーフ》とは、「喪失によって引き起こされる悲嘆のこと」である。
▽ 再定義に至る思索
喪失によって引き起こされる悲嘆
二点、大きく注目しておきたいことがある。
一点目はグリーフの原因となる「失う」が、厳に「消失」ではなく「喪失」であるという点である。グリーフの発生はある対象の「存在の消失」に起因するのではなく、その「ある対象」を認識する者にとってのそれとの「関係の喪失」に起因するものである。
例えばV・ジャンケレヴィッチの言うところの「三人称の死」においてはグリーフは存在し得ない。しかし逆に「一人称の死」おいてグリーフは存在し得る。それはある人の自分自身との関係認識、言い換えれば「アイデンティティ」の喪失によってグリーフが引き起こされるからであるが、ここに自分自身の「消失の事実」は存在しない。
従ってグリーフが「あらゆる」死によって引き起こされるという考えは、倫理的・理想的・人間的ではあるが、論理的ではない。そして逆にグリーフの発生は「死の事実を待たない」という点にも十分に留意すべきである。
二点目はグリーフを引き起こす「喪失」の具体的事象が「死別」に限定されないということである。現在の日本において『グリーフ』が訳される時、それは「死別の」「特に死別の」と冠せられることが一般的だが、これは殊更に死を忌避すべきもの、それに伴って死別の悲嘆を人の悲しみの中で「最上位のもの」であると考えがちな我が国における戦後的発想が表れているのではないだろうか。
確かに死別の悲嘆は人の悲しみの中でも格別強い感情として表れやすい。しかし死別のほかにも「失恋」に代表されるような関係の喪失においてグリーフは発現され、またその強度もそれまでの関係性の強弱に依拠する度合いが高く、具体的事象そのものに限定的に帰着するものではない。卑近な例では「引越」に伴う親友との別離、「失業」に伴う一社会との関係喪失、あるいは子どもが愛着のある玩具を捨てられてしまった時の悲しみも、グリーフであり同様の性質を持つ。
我が国において「グリーフ」という語が用いられ始めたのはごく近年のことであるが、その範囲は心理学や精神医学の分野を除けば葬儀業界や宗教界にほぼ限られている。このこと自体が前述の「グリーフ=死別の悲嘆」という認識に一役買っているわけだが、業界の大衆に対する情報アプローチがその認識を前提にしているために、逆にグリーフが「普通でないもの」「あってほしくないもの」であるかのように受け止められ、大衆にとってその理解を進めることの敷居を高めているのではないかという懸念がある。
しかし前述のようにグリーフ自体はその程度の強弱はともかく至極「人間的な」当たり前の、誰もがいつでも持ち得る感情である。そのことから言っても人は基本的に個々人が自分自身の精神衛生を保てる最低限の自己回復力を有している。その認識に立たない高飛車な、また事象に対して一辺倒なケアは危険であり、回復を助けないばかりかグリーフをさらに深刻なものにしてしまう可能性もあることには十分に注意しなければならない。