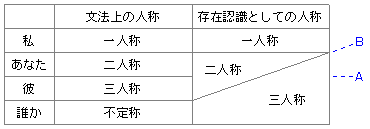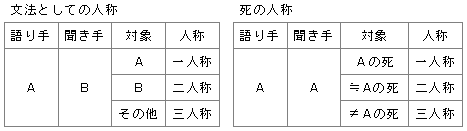死の人称
※ 以下の記事は2011年1月10日〜13日の筆者のブログ記事を一部調整して転載したものです。
▽ ジャンケレヴィッチのいう「死の人称」とは
近頃どうも 哲分 が足りないためか 知 の巡りが悪いので、久しぶりにジャンケレヴィッチの『死』(みすず書房,1978)を手に取りました。ジャンケレヴィッチといえばよく引用されるのが「死の人称」ですが、前々からどうももうひとつよく分かっていなかったのが「二人称の死」と「三人称の死」の境目はどこかという点です。
「人称」を辞書で引くと次のようにあります。
【人称】話し手との関係を表す文法範疇。話し手自身を指す一人称(自称)、話しかける相手を指す二人称(対称)、それ以外を指す三人称(他称)の三種に分ける。…広辞苑 第五版,岩波書店
これ自体はよく知られたことで、中学校の英語の授業で習う「I・you・it」をよく例示として引き合いに出されます。「死の人称」についても例えばwikipediaでは「死」の項目4-2で「三人称の死」について「三人称の死:英語での人称「it」「he」「she」などにあたる。いわばアカの他人の死。二人称の死が取り替えのきかない存在なのに対し、他の他人の死でも置き換えられる点に特徴がある。…」と説明されています。
しかしジャンケレヴィッチは「死」においてこう述べます。
…第三人称の死は、死一般、抽象的で無名の死、あるいはまた、たとえば一人の医者が自分の病気を検討する、ないしは自分自身の症状を研究する、あるいは自分自身に診断を下すという場合のように、個人の立場を離れて概念的に把えられたものとしての自分自身の死だ。(p25)
wikipediaの説明の後半はともかくとして、前半はどうなのでしょう。葬儀士の立場を例に取って具体的に考えるなら、さっき連絡を受けて病院に迎えに行き始めて出合った「現在目の前にいる死者の死」は二人称か三人称か、という問題です。医師から見た患者、という例では医師が「○○の病気に罹っている患者」という場合については三人称だと言えるでしょうが、「この患者」という時にそれが「it」であるからといって「三人称の関わり」であると言えるでしょうか。
ジャンケレヴィッチの定義からすると、その死者の唯一性があるかぎり、つまりは人格的な存在の認識という点においてその死者がその死者でしかないならば、その死は「抽象的で無名の死」と言えないのではないか、という疑問が湧くわけです。すなわちジャンケレヴィッチの言う第三人称は代名詞「彼」ではなく「誰か」であると言えるのではないでしょうか。
では例示した死が「二人称の死」であるかといえば、それも正しくはないようです。ジャンケレヴィッチによれば二人称の死とは次のようなものであると述べられています。
…第三人称の無名性と第一人称の悲劇の主体性との間に、第二人称という、中間的でいわば特権的な場合がある。遠くて関心をそそらぬ他者の死と、そのままわれわれの存在である自分自身のとの間に、近親の死という親近さが存在する。たしかに”あなた”は第一の他のもの、直接に他である他、”わたし”との接点にあるわたしならざるもの、他者性の親近の限界を表象する。そこで、親しい存在の死は、ほとんどわれわれの死のようなもの、われわれの死とほとんど同じだけ胸を引き裂くものだ。…(p29)※太字部は原書では傍点
これからすると、葬儀士が目の前に現にいる死者に対して「胸を引き裂かれるほどの衝撃を覚えなければ」、それは二人称の死とも言えません。つまり二人称の死とは「親密性の認識」をその基準としているのであって、相手が「代名詞でどう表現されるか」が問題なのではないということになります。
さて、根本的な問題として冒頭に引用した文法範疇としての「人称」と、哲学的な存在認識としての「人称」のズレが生じていることはわかります。図にすると次のようになるでしょうか。
一人称の死においては文法上も哲学上も変わりはありませんが、二人称以下はほとんど違うものを指しているようです。この状態で三人称の死を「he」などにあたる、というのはあまり適切ではないと思えるのです。
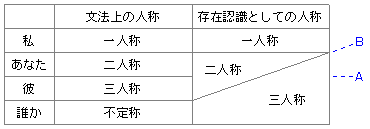
このジャンケレヴィッチにいう「二人称の死」と「三人称の死」の間に浮遊する「彼」にひとつの解決を見出そうとしたのは、ノンフィクション作家の柳田邦男(民俗学者の柳田國男ではない)という人物だそうで、彼の提案したのは「2.5人称の死」という概念でした。彼は医師から見た治療対象としての患者などについて、それが人称の分類状は「三人称の死」でしかないという前提に立ちながら、しかしその患者の大事な場面で密接な関わり合いを持つ医師は決して三人称ではなく、より二人称に近い「2.5人称の関係性」にあると呼ぶことを提案したい、と述べています。(参考ページ)柳田もその提言の下敷きとしてジャンケレヴィッチの「死の人称」を引用しています。そのため「2.5人称」の位置する場所も文法上の二人称と三人称の境目(図のAライン)ではなく、存在認識としての人称における二人称と三人称の境目(図のBライン)上にあると考えてよいと思います。
しかし先般の表では結局のところジャンケレヴィッチ自身が浮遊する「彼」をどう位置付けたのか…いやそもそもジャンケレヴィッチが文法上の「人称」と違う概念に対し「なぜ同じ『人称』という言葉を用いたのか」が説明できません。私は何を誤解しているのでしょうか。
ジャンケレヴィッチは『死』の中でこの「人称」についてこうも述べています。
…一方、すべての人でありながらだれでもない無名の《ひと》と、他方、わたし自身との間には、《わたし自身》ということばでわたしなるもの、つまり、第一人称という文法上の概念ではなくて、端的純粋に《自分》、冠詞なしのわたし、まさにこの場でこの瞬間に”わたしが…”と言う自分を理解するとき、その相違はまことに形而上学の分野に属する。語るわたしは、他のすべての死すべき者と同じ一人の死すべき者でも、生きとし生けるものの間の一個の生けるものでも、一人のどれでもよいカイウスでもなく、説明しようがないほどに特権的な一人の人間なのだ。…(p22)※下線は筆者が追加
…もっと明確に三つの人称、つまり三つの視角を区別しよう。第三人称および第二人称は他者(かれあるいはあなた)に対するわたしの観点あるいは他者のわたし自身(他者の第三人称あるいは第二人称とみなされたわたし)に対する観点であり、たがいに相手となる二者は、モナドとしても、また個人としても、異なった二つの主体のままだ。わたしのわたしに対する観点、あなたのあなたに対する観点、そして一般的には各人の自分自身に対する《再帰的》観点である第一人称、この観点は遠近法および視覚距離を放擲するものだから、かろうじて《観点》と言えるものだが、この視角が、実際のところ、意識の対象と《死ぬ》の主語とが合致する自分自身の死の生きた経験だ。…(p24)※下線は筆者が追加
………。 なんのこっちゃ (ナイアガラの滝汗
この二つ目の引用の直後に、初め引用した「第三人称の死は…」という文が続きます。そしてそのしばらく後、
…わたしにとってのあなた及び彼である第二人称、第三人称も、自身に対してはわたしではないだろうか。各人称はその人称自体にとっては、つまりそれ自体として、それ自体の観点から見て、再帰的に第一人称ではないだろうか。わたし自身ではないが、かれ自身にとってはわたしである他者、この他者は、単に《わたしのよう》であるにすぎない。この角度から、間接的に自分自身の死はふたたび普遍的なものとなる。…(p26)
こういうことでしょうか。
ジャンケレヴィッチが死を考える際に、その登場人物は自分(A)しか存在しない。いや現実には存在するけれどその存在は結局のところ「その人にとっての自分(A')」であるから意味をなさない。AはAに対して「死」を語るが、その際に対象とされる「死」が「Aの死」である場合は一人称、「Aでない(あるいは特定できない)人の死」であれば三人称、「まるでA自身の死であるかのようにA自身に感じられる死」が二人称の「死」である。
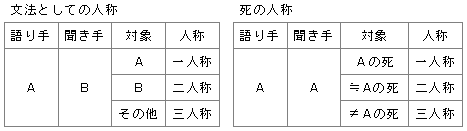
すると誤解しているのは、ジャンケレヴィッチが「死の人称」と言ったのは認識者と死者との関係性の話ではなく、その「死」の、認識者からの距離であるということではないでしょうか。認識される「対象」はあくまでも「死」であって、「死者」ではないのではないでしょうか。
そうだとするとつまり、「一人称の死は自分の死、二人称の死は大事な人の死、三人称の死はどうでもいい人の死」というよく聞かれる説明はある意味で誤りでしょうし、「現在目の前にいる死者の死は二人称か三人称か」という設問自体もジャンケレヴィッチの「死の人称」を土台に考えるには 的外れ なのです。
もしこの通りだとすれば、ジャンケレヴィッチのいう「死の人称」において「2.5人称」や「4人称(※)」などは当然ありえないわけです。「自分でなく」「自分以外のものでない」死について、自己と他者の境目、その線上にあるという「あいまいな」死のみをジャンケレヴィッチは「二人称の死」と呼んだのですから。
(※)柳田の言う2.5人称を3人称と再定義して、ジャンケレヴィッチの言う3人称を「4人称」と呼ぶ人もいるそうなのです。
ではなぜ我々は「2.5人称の死」などを想定しなければならなかったのでしょう。それは我々の想定した「人称」が「死」のものではなく「葬送」のものだったからではないでしょうか。つまり、ジャンケレヴィッチにおける「死の人称」は聞き手が語り手自身であるのに対し、「葬送の人称」は聞き手が「死者」であることに違いがあるわけです。つまり2.5人称や4人称の発生は、認識される対象としての「死」と「葬送」の間の「揺らぎ」だったのだと結論付けられるのではないでしょうか。
この前提に立って再定義するなら、
第一人称の葬送 = 自分の葬送 「私の葬送」
第二人称の葬送 = 死者の個別性(人格)が認識されている葬送 「ある人の葬送」
第三人称の葬送 = 特定されない葬送一般、抽象的な概念としての葬送 ただの「葬送」
となるでしょう。
こうすることでまた、「葬送の人称」において2.5人称や4人称は存在しえなくなり、浮遊する「彼」の葬送についても確定します。たとえ「その死者」がどこの誰かわからなかったとしても、「今目の前にいる」という事実によってその死者の個別性は確認されるからです。
そうすれば「小数点以下の死者区分」が無制限に増殖していくこともありませんし、そのことによって「死者や葬送の重要度ランク付け」が行われることも防ぐことができます。
ところでここで気付くのは、上記のように再定義した場合、「具体的に実行される葬送はすべて第二人称の葬送でしかありえない」ということです。考えてみれば至極当然の話ですが、改めて言葉にしてみると面白いですね。